目次

その理由は、ピアノに対して恐怖を覚えてしまったからなのです。そうなってしまうと当然楽しいなんて思えることもなく、嫌なものを「嫌だ」と言うこともできないまま、ただ続けているだけでした。
そんな私に小学6年生の時、運命の出会いが訪れます。それは私の音楽に関しての感性までもを変える程の出来事でした。
今でも思います。「この出会いがあったから今の自分がいる」と。
その経験を通して、今現在「好きで始めたはずなのになにも楽しくない」と悩んでいらっしゃる方のお力に、少しでもなれたらと思います。もちろん音楽以外で同じように悩んでいらっしゃる方にも。
感性が変化することで、自分が悩んでいる事に対して、心持ちから何からすっかり変わるのだということをお伝えできればと思います。
最初のピアノ教室で植えつけられた恐怖

ピアノを始めたきっかけは、幼稚園に通っていた同級生たちが皆通いだしたことからでした。
「自分もやってみたい!皆と楽しみたい!」そう思って、幼稚園で週1回開かれていた某ピアノ教室へ通うことにしました。
最初は楽しかったのです。音符の見方や音の高さなどを、道具を使って1から学んでいきます。そしてある程度学習したところで一番簡易な楽譜を渡され、一音一音確認しながら楽譜を見て弾きます。
合格すればその楽譜にはシールが貼られました。今思えばそれが嬉しく、シールを貰いたくて私はレッスンに通いました。
ただ1つ問題がありました。それは、私が小さい頃から多汗症であったことです。
20歳になった今日も変わらないのですが、緊張したり物事に夢中になっていたりすると、とたんに手のひらに汗をかき、手がびっしょりと濡れてしまうのです。
「手汗がなんだ」「緊張したら手汗かいたって仕方ないじゃん」そう思うかもしれません。しかしこの教室の先生にはそれは伝わりませんでした。
ピアノを弾いたり演奏したりしていると手汗が鍵盤につき、それは色が変化して目に見えるものと化します。それがこの先生には我慢できないことだったのです。
汗で汚れた鍵盤を見た先生に言われた言葉を、今でも覚えています。汚れた鍵盤を指さして大きな声でこう言ったのです。
「先生こんなん嫌いです!洗ってきなさい!」と。
もちろんそれは、気を付けてどうにかなるものでもなく、私はただ先生の指示に従って、手がキンキンに冷たくなるまで洗うしかありませんでした。
冷たく、凍えた状態の手で上手にピアノなど弾けるはずもありません。しかし先生はその時に限って上機嫌で、私の演奏ではなく汗で汚れない鍵盤の方を褒めました。
「今日鍵盤汚れてないじゃん!先生こういうの好き!」と。
演奏できる状態で演奏すれば怒られる、怒られないようにかじかむぐらい手を冷やして演奏すれば、どんなに演奏がめちゃくちゃでも汗をかかないことを褒める…。
そんなの私が望んでいたピアノレッスンではありません。ただ怒られないように従っているだけで。
音楽教師の母との壮絶な自主練。冷めてゆくピアノへの情熱

私に恐怖を植えつけたものがもう一つありました。
ピアノ教室のレッスンで曲として見てもらうためには家での自主練が必要なのですが、いつも付きっきりで教えてくれた母の教えが私には全く合わなかったのです。
なぜか、母は過去の自分と私を比較してくるのです。そしてすぐ怒られるのです。
「私はこうだったのになんで貴女は~」「なんでできないの!」
母は音楽の教師をしていてピアノと歌ができるため、そう言われてしまうのは仕方のないことだったかもしれません。しかしそのせいでレッスンは楽しくないし、母の教えは怖い上イライラするし…。
母に自主練をみてもらった後は涙が止まらなかったのを覚えています。結果的に、興味を持って始めたはずのピアノが恐ろしくなり、幼稚園時代の私の心はピアノから次第に離れていきました。
小学生時代の恩師との出会い。しかし母との自主練は続く
小学校に上がってからは別のピアノの先生のもとへ通わされたのですが、この2人目の先生が実はとても素晴らしい方でした。
今でも恩師と慕うこの先生に教わるようになってから、あれほど苦しめられ、恐怖まで覚えた「鍵盤の汚れ」で怒られることがなくなったのです。
この恩師に高校3年までの12年間ピアノを教わり、私は再びレッスンの楽しさを取り戻したかに見えました。

しかしレッスンは楽しくても,やはり自主練をする私の隣にはいつもあの母がいました。母のこれ駄目あれ駄目の連呼が止むことはなく,怒られては涙する日々が続いていたのです。
大好きな先生になってレッスンは楽しくなったのに、自主練が辛いために家での練習を怠り、私は日に日に下手になっていきました。
自分から進んで練習していると母が横から首をつっこんできます。母は私の背後に立ち、なにか間違いはないかとか、手首は下がってないかなど、じっと見下ろしてくるのです。
練習を怠れば当然母に怒られ、練習したらしたで、かならず母になにか言われる。その恐怖から私は再びピアノから遠ざかりました。楽しいはずのレッスンでは、その練習を怠ったことを隠すのに必死になりました。

さらに母がいない時は父が私の練習に首を突っ込んできました。私は中学生になるまで父が嫌いでした。私のことをいつまでも3歳児のように扱う父に嫌気がさしていたのです。
ピアノを練習している時も、私のことを実年齢より下に扱う父の口調は変わりません。言い返せばきつい言葉で言い返され、とても反論なんてできませんでした。
「練習しても演奏しても、自由に弾いても、結局ガミガミ言われるだけだしなあ…」
今思えば足が遠のいて当然だと思います。特に他者からの指摘が嫌いな私はそうだと思います。
なんでピアノを続けているんだろう…。そんな答えが出ないなかで悩む日々がずっと続きました。
褒められたいのに、褒められない。

母の怒り方で私が最も嫌なものがあります。それは「人と自分を比べ、対象の人を見下し、自分を持ち上げる」ことです。
例えばピアノを練習しているときなど、呆れた様子で私の背後からこう話しかけるのです。
「あなたって○○と一緒でこういうとこあるよね」「お母さんはこんなの簡単に弾いたよ」
また、ピアノ以外でも私がなにかに挑戦するのを止めるかのように、同じような言葉を投げつけられていました。
母はなにかにつけ、自分の方が上だと誇示してきました。私が何か事を始めようとする度に「私はこうだったけど、あなたはこうだからだめ」と自分の過去を誇示し、私を見下し、新たなスタートをさせてくれようとはしませんでした。
それゆえ、私は何かを始めようという意思が自然と萎えてしまうのです。どんなに頑張ったり努力したりしても、母は私を褒めることはありません。
自分を持ち上げ、私を見下し、呆れた口調でいつも私に話すのです。あたかも「その程度でなんでそんなに喜べるの?」とでも言うかのように。

しかし幼かった私は母から褒められたかったのでしょう。怒られても見下されても目に涙を浮かべながら練習をしました。
「母に褒められたい」という一心だった心とは裏腹に、私には怒られるか否定されるかのどちらかしか選択の余地はありませんでした。そんな状況で音楽なんぞ楽しめる余地もありません。
音楽に携わってない時、それが一番こころ安らぐときでした。今思えば、あのころの自分は自分じゃなかったなと。
「結局は自分が1番上なのね」子供ながらに、何度もそう思ったことを覚えています。
訪れた運命の出会い
小学6年の5月、私は母に連れられ、とあるコンサートに足を運びました。
それは「和太鼓松村組」という世界の音楽を融合させたチームの公演でした。
「和太鼓松村組」は、1995年に関西を襲った阪神・淡路大震災で被災された方々への激励と神戸の復興エネルギーを全国に発信することを目的に、神戸で発足したチームです。組長は松村公彦さんが務められています。
「和太鼓松村組」は、和太鼓の持つ響きの神髄に迫りつつも、マリンバやオカリナなど南米アンデスの民族音楽との融合を図り、独自のサウンドを追求されています。
「和太鼓が好き」というとよく「しぶいなあ」や「楽しいの?」などとよくいわれます。
私も以前は和太鼓にまったく興味がありませんでした。
和太鼓というと、よく見るお祭りのような雰囲気のイメージが強いため、地鳴りのような音が響いたり、男達の威勢のいい声が飛び交うものではないのかと思うかたも多いでのはないでしょうか。
ですが松村組のコンサートはそんな予想を大きく覆しました。
初めて聞きに行ったコンサートは小さな木造のホールが会場でした。私は今でもその時の感動を覚えています。

今まで味わったことのない音楽の世界観、そして聞いていて「すごい」「格好いい」「素敵」といった様々なプラスの感情が胸の内から湧き上がりました。
和太鼓の力強く身体全身に響き渡る重音、マリンバの優しい柔らかな音色はときに鋭利な固い音へも変化します。日本の横笛である篠笛の甲高い音は決して耳にキーンと響いてくる音ではなく、胸にジンと響いてくる音なのです。

そして私が初めて見た南米アンデス地方の民族楽器の1つ、ケーナ。(1分08秒〜1分15秒参照)
渡辺勝喜さんという方が演奏されているのですが、尺八に似た竹笛のはずなのに、とても優しく私たちを包み込むような柔らかい音を醸し出し、聴く人を虜にします。
私はそんな松村組が創り出す世界にどんどん引き込まれていきました。次はどんな曲が待っているんだろう、なんの楽器が使われるんだろう、と、こんなワクワクと心躍る感覚は初めてでした。似てはいるけれど、全然国が違う国の楽器が融合することでこんなに素敵な演奏が繰り広げられるのかと。
「音楽に国境はない」とはまさにこのことだと思いました。そして「音楽って楽しいんだ」と初めて実感しました。
そのステージを聴いてから私は松村組のファンになりました。何度もステージに足を運び、感動感激し、エネルギーを貰っています。
そして、音楽以外の感性も大きく変わりました。自身を表現することが楽しくなり、少しかじった程度だった執筆や絵を描くことにも興味が膨らみました。
松村組と出会う前と出会った後の私を比較すると明らかに違います。怒られるからと背を向けていた音楽に正面から向き合い、練習するようになりました。たとえ怒られたり、文句を言われたとしてもめげることはなくなったのです!
「和太鼓松村組」との出会いで得た人生の起点

その後、中学校で入部した吹奏楽部では打楽器パートを担当し、高校では和太鼓部に入部しました。大学は音楽学部に進学と、私は音楽の道を歩みはじめました。
今はピアノと声楽を恩師のもとで学び、趣味では執筆、人物の描写、ポエムづくりなどを楽しんでいます。
小学校以降の人生がこんなに音楽で彩られ、自己の表現を楽しめているのは松村組との出会いなしには語れません。「運命のひと」といっても過言ではありません。
小学6年生の時の運命の出会いが後の私を創り上げていくとは、当時の私は思ってもいませんでした。松村組は私の新たな人生の起点なのです!
「楽しい」という気持ちから広がった世界の心地よさ
松村組から「心から楽しむことの大切さ」を学んだ私は、それから両親がいない時間帯をみつけて自分で練習するようになりました。
すると、自分の得意な面や苦手な面が見えはじめ、苦手な部分があれば克服したい!と思える意思も出現しました。そしてさらに難易度の高い曲、有名な曲にチャレンジしたいとも思うようになったのです。
自由に、誰にも批判・口出しされずに演奏することの楽しさ。私は初めてそれを身を持って体感したのです。以前は何も言えずにいた母にも「自分で練習したいから口出ししないで」と伝えることもできました。
母は当初「本当に出来るの?」「心配なんですけど」と口を出していました。しかし私が真っ向からピアノに向き合い、母の態度に異を唱える姿勢を示すようになってからは、徐々に私の練習への口出しは減っていきました。

そうして自分の思うがままに練習を繰り返す日々のなかで、今までにない楽しさが心の底から湧き上がってくるのを感じました。また技術も着実に向上していきました。
私が「楽しい」と思えるようになったことで、ピアノに真っ向から向かい合えるようになっていたのです!
それからというもの、レッスンでは課題に出された曲を次々に弾きこなし、合格するスピードが上がりました。またピアノ1曲1曲に対する心構えも変わり、曲のイメージや情景を自分なりに想像しながら、目の前の楽譜に真剣に打ち込むようになりました。
運命の恋人の名は…

それから月日が過ぎ、高校生になった私に初めての恋が訪れました。
相手は高校1年の時に発表会で演奏したベートーヴェンの『テンペスト』第3楽章。
この曲に取り組み始めてからというもの、私の頭の中には常にこの曲が流れ続けました。当然曲への打ち込み方は今までで1番。通学中もたえず口ずさみ、家に帰るとすぐにピアノに向かいました。
また高校3年生のラストステージでも私は運命的な出会いをしました。
憧れているピアノ奏者の方がベートーヴェンの『熱情』第1楽章を演奏される姿を以前見て、いつか私もこの曲を演奏してみたいという願望を心に抱くようになっていました。その願いが、高校のラストステージで叶えられたのです!

「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、本当にその通りだと思います。松村組に出会う前の私と、高校時代の私を思い返せばそれが明確にわかります。
すべての趣味にいえるのですが、恐怖や苦手といった負の感情に支配されていては楽しむものも楽しめませんし、上達なんて望むべくもありません。自身に楽しむ意思があってこそ初めて上達するのです。
もっと上達したい、表現したい、他者に楽しんでもらいたい。私の思いはさらに高みを目指していました。
そんな折、嬉しいことに昨年演奏会で演奏してくれないかと声がかかり、私はピアノを演奏する機会を得ました。
「演奏よかったよ!」「上達したね!」と声をかけてくださったのは、まさに筆舌に尽くしがたい喜びでした。
またそのときに担当させていただいたMCでも高評価をいただいたき、さらなる喜びとなりました。
今年の夏もコンサートに出演させていただくことになり、現在本番に向けて練習中です。
「1つの物事に関して『楽しい』という気持ちを知らずして本当の楽しさは得られない」。それを強く実感しました。
まとめ

今私はピアノ、声楽、趣味を自分のペースで楽しんで取り組んでいます。またピアノ、声楽共に恩師3人と巡り合うことも出来ました。
時々つまずいたり、落ち込んだりすることもありますが、それでも楽しめるからこそ上達していけるのだと思います。
松村組と出会って、私は「心から楽しむことの大切さ」を学びました。
- 自分が慕う恩師や先生にアドバイスを受けながら、自分のやりたいように演奏し、やりたいように表現する。
- 少しずつ目の前の壁を突破しつつも、誰かからの批判、否定に振り回されず、己が表現したい演奏を貫く。
それを実現した時の楽しさ、嬉しさが本当に心地いいのです。
ある時YouTubeを見ているとその時に「ちやほやされるのも一瞬。誰かからの批判も一瞬。」という言葉を見ました。
確かにその通りです。ただ一度の批判に振り回されて自分の人生を左右されていては、あまりに間抜けです。
自分の人生を決めるのは自分なのだから。

あの時松村組に出会わず、両親にガミガミ言われながらの練習を続けていたら、確実に私は今音楽に携わっていません。音楽=怒られる種、になっていたのですから。
どんなに大変なことでも、一度なにか小さな楽しさを体感すれば塞いでいる目の前の壁を壊し前進したくなります。また、壁をひとつクリアすれば、更に難易度の高いものに挑戦したくなります。
それが「楽しむことの大切さ」てす。何事も楽しまなければ意味がないのです。
ただやらされているだけ、ロボットのように従っているだけでは、なにも自分にとってプラスにはならないのです。

繰り返しになりますが、「好きこそものの上手なれ」とは本当にその通りだと強く思います。
音楽の楽しさに気づかせてくれた松村組に心から感謝しています。松村組がいなければ今の自分は絶対存在しません。
もし松村組と出会ってなければ今私はなにをしているのでしょう。ピアノから離れ、そして大好きな筈の音楽から逃げ、もう一つの好きなジャンルである歴史を堪能していたのでしょうか。
想像がつかない程に私の中で松村組が大きな存在になっています。彼らに出会えたからこそ、今を楽しめているのです。そしてこの文章を書いているのも松村組に出会えたからこそなのです。
音楽を堪能出来るようになったことで、自分を表現することが本当に楽しくなりましたし、それを他者に楽しんでもらえることが何より私にとって嬉しいのです。
時にぶつかり、落ち込むようなことがあっても「楽しむ」ことを忘れずに、これからも大好きなピアノや声楽、そしてたくさんの趣味と真正面から向き合い、学び、そして付き合っていきたいと思います。




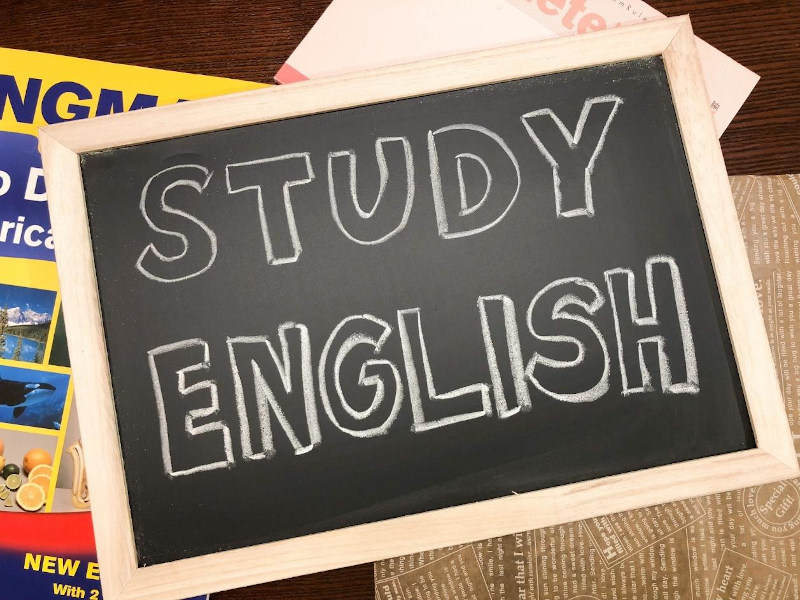



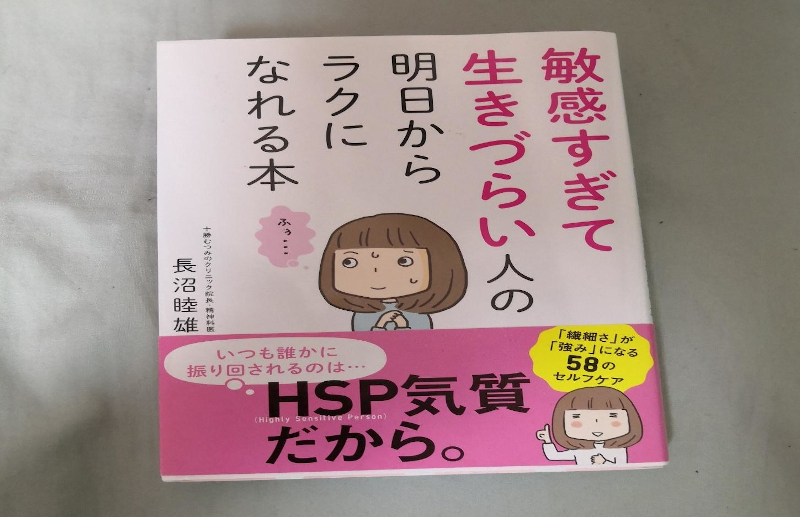
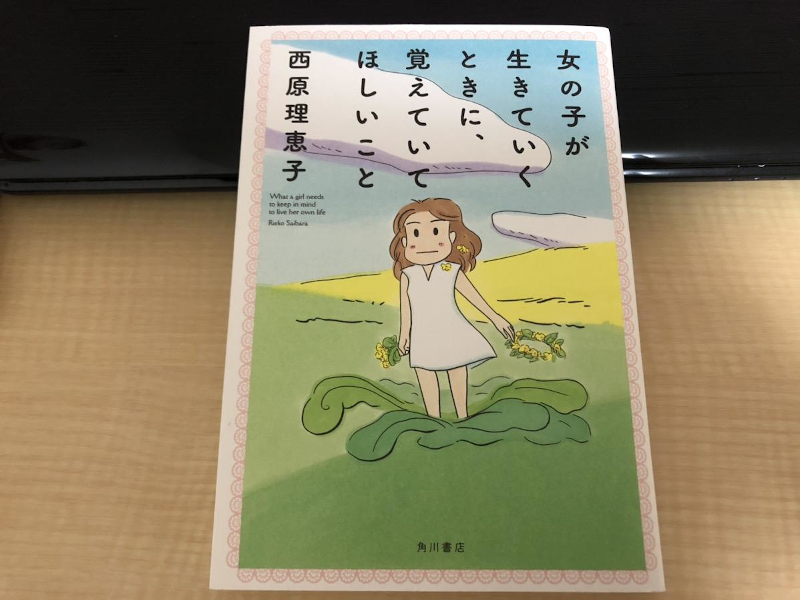


大学2回生、音楽学部所属 将来の夢は心理カウンセラー
趣味は執筆、人物の描写、ポエム作り、アテレコ、旅行
日本の文化(和や古)が大好き
音楽、歴史にロマンを抱いている
現在、社会勉強しつつ、たくさんの方々に支えられながら色んなことに挑戦している
近々コスプレに挑戦する予定